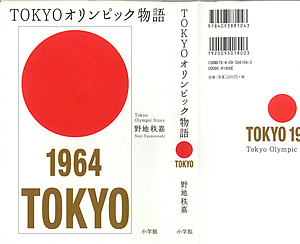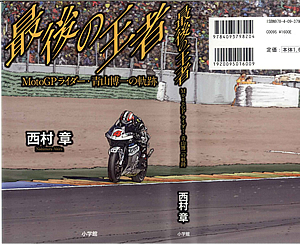第24回/2013年度
■最優秀賞 (トロフィー、副賞100万円)
アイスタイム 鈴木貴人と日光アイスバックスの1500日

伊東 武彦(いとう たけひこ)(発行:講談社)
選評:
本書は、アイスホッケー日本代表のキャプテンを長く務めた名選手、鈴木貴人を軸に、鈴木が選手生活の最後に活躍した日光アイスバックスの闘いぶりと選手たちの群像を描き、その背景に日本のアイスホッケー50年の歴史を浮かび上がらせた、なかなか手の込んだ労作である。第一章暗闇、第二章変化、第三章時代、第四章逆襲、第五章断裂、第六章薄明と章立てされており、章のタイトルは鈴木とアイスバックスのその時々の境遇に即したものとなっている。
栃木県日光市に本拠をおく古豪、古河電工アイスホッケー部が廃部を発表したのは1999年1月。存続を求めるファンは4万を超える署名を集め、アイスホッケー界、地元自治体、古河電工の支援のもとに日光アイスバックスが1999-2000シーズンに誕生した。財政は常に危機的状況にあり、給料は遅配、成績も上がらない。そんななか、コクドと西武鉄道という名門チームが合併して出来たSEIBUプリンスラビッツが2009年に廃部になり、日本を代表するフォワードの鈴木貴人がバックス入りした。バックスの監督は、鈴木と同年齢で苫小牧での小学生時代からのチームメイト、村井忠寛であった。
えのきどいちろうとセルジオ越後が経営に参画して好転を期したが果たせず、2010年には吉本興業の傘下にあるスポーツマーケティング会社を経営する、ライセンスビジネスの専門家がチームディレクターに就任する。
日本のアイスホッケーは札幌五輪に向けての選手強化を目的に1966年に日本リーグが始まり、1970年代に黄金期を迎えた。堤義明が1972年に国土計画アイスホッケー部を作り、73年に日本アイスホッケー連盟会長に就任。75年の優勝決定戦はリーグ代々木競技場に1万2千人が集まり、77年の世界選手権でも代々木競技場は最上部まで埋まった。日本代表は五輪にも出場、世界は遠いものではなかった。同じ頃、サッカーは平均1千人の観客しか集まらず、W杯予選、五輪予選も5回連続敗退とどん底を味わう。しかし、プロリーグ化へと舵をきっていくサッカーと徐々に立場が逆転し、明暗がはっきり分かれて行く。そして2004年、堤が失脚した。
2011-12シーズン、財政が安定した日光アイスバックスは補強に成功し、開幕6連勝を飾って、初めてアジアリーグのプレーオフに出場。さらにはファイナルに進出して、最終戦で同点に追いつく。その後突き離されて惜しくも2位で終わったが、2千人で満員の霧降アリーナは同点だった数分間に至福を味わった。
翌季、経費節減のための主力の放出、残った主力の相次ぐケガでバックスは低迷する。シーズン終了後、村井監督は辞任。肉離れで大事な局面でプレーできなかった鈴木も引退を考える。
2013年4月、世界選手権ディビジョンIAでの代表を最後に、鈴木は引退した。
出来事を追ってあらすじに起こせば、このようになる。しかし、本書の魅力はこのあらすじにはまったく表れない。それは一見未整理に見えるユニークな叙述の構造によるところが大きいからだ。
第1に、アイスホッケーの試合描写がある。本書のタイトルの「アイスタイム」とは、アイスホッケーで選手が氷上でプレーする時間のことだが、選手交代が頻繁に行われるアイスホッケーでは1回がたった40~50秒のアイスタイムを1試合中に何十回も繰り返し、チャンスとピンチが目まぐるしく訪れる。ここで著者は「・・・した」「・・・だった」と「た」を重ねて畳みかけるように話を進め、これがまさにアイスホッケーの試合展開によく見合っている。随所に展開される実際の試合運びの描き方はまるで実況放送を聞いているようで無駄がない。アイスホッケー初心者に向けての注釈も付記され、アイスホッケーをまったく知らない者でも、迫力やスピード感を想像できる。
第2に、そこに登場してくる多くの選手たちについてその生い立ちや戦績、思いの丈や悩みが語られる。ここは周到な調査やインタビューが裏付けになっていることが伝わってくる。そして第3に、もう少し引いて、日本のアイスホッケー誕生の経緯やその後の展開、サッカーとの比較、チームの経営、ファンの動態、さらには堤義明の功罪など、大きな話題が出てくる。この3つの次元が次々と連鎖して展開し、試合から選手へ、さらには経営問題へ、再び試合へというように行きつ戻りつする。これは一面、混乱を招くようにも見えるが、読んでいるとむしろ自然に話題の発展についていける。試合だけを延々と書き綴るのではなく、今シュートしたその選手はこういう人なんだ、という語りの広がりを楽しめる。あまりに登場人物が多くて混乱する読者もいるだろう(巻末に登場人物紹介が付されている)が、退屈しないで読み進められることは確かだ。
霧降アリーナは2千人しか入らないが、アイスバックスのファンは事あらばすぐに募金活動で数百万を集め、贔屓選手のジャージのオークションには大枚をはたく。どの選手にもファンがいて、アリーナは勝ち負けに関係なく盛り上がり、幸福感が漂っている。他のプロスポーツやエンタテインメントを見て来たチームディレクター日置は、バックスは一種の宗教のようなものであり、霧降アリーナは神社なのではないかと仮説を立てている。その教義は、勝敗は別にして最後まで諦めない気持ちを持つこと。たまにしか勝てなくても、最後まで戦う姿勢に人々は共感し、選手と一体になって試合に我を忘れる。地域のプロチームの一つのあり方、サポーターとの一体感の作り方を日光アイスバックスは例示しているのかもしれない。
世界が遠いマイナー競技、恵まれない待遇、そんななかでもプレーを続ける選手たちはどんな人たちで、アイスホッケーの何が魅力なのか。著者は多くの材料を提供して読者に伝えようとしている。
著者は元『週刊サッカーマガジン』編集長で、『AERA』でも人物評伝を手がけた人だけに、試合描写、人物描写ともしっかりしており、乾いた筆致は好感が持てる。
冬季五輪を前にした時期の作品であり、女子代表チームの活躍で興味を持った読者に、さらにアイスホッケーへの関心をつなぐ出版である。
■優秀賞
アメリカの少年野球 こんなに日本と違ってた

小国 綾子(おぐに あやこ) (発行:径書房)
選評:
元新聞記者の母親と小学3年生の野球少年の息子は、父親(新聞記者)の海外赴任に伴い、2007年9月から4年間アメリカで暮らすことになった。息子はアメリカの少年野球チームに入ることにするが、言葉の壁、文化、価値観のギャップ、きびしい競争、親子は想像もしなかったさまざまな試練に直面することになる。本書は、そんな親子のアメリカ異文化体験記であり、過去にはあまり類似作品のないジャンルの秀作である。
著者一家が暮らしたのは、ワシントンDC郊外のメリーランド州ロックビル市。美しい天然芝が標準装備のアメリカの少年野球場に心を躍らせたのもつかのま、息子太郎(仮名)は、英語をしゃべろうとせず、サイレント・ピリオド(沈黙の期間)は延々と続いてなかなか友だちができない。ようやく春の野球シーズンが訪れ、著者は期待に胸をふくらませ息子を近隣の少年野球チームに登録するが、日本とは異なる少年野球のシステムに当惑する。アメリカにはリトルリーグだけでなく民間団体などのさまざまな野球リーグがあり、そのなかも娯楽目的、楽しむ野球が中心のレクレーションチーム(レクチーム)と、トライアウト(選抜試験)に合格した子達が所属し、地元のリーグには参戦せず州外などに遠征してトーナメント大会に出る競技志向のより強いトラベルチームとに分かれている。選択肢がたくさんあり、自分の子どもに何が最適かを考えるのは親の責任、親の情報収集力やコミュニケーション能力が問われる。レクチームとトラベルチームとの技術の差は歴然、当初はレクチームに息子を入れた両親だったが、悩んだ末、紆余曲折をへて翌シーズンからトラベルチームに入れることになる。
それからも親子はさまざまな困難に直面するが、それはアメリカのスポーツ、アメリカの価値観に対する新鮮な驚きを伴うものでもあった。集中と積極性(フォーカス&アグレッシブ)を強調するコーチングにおいては、アグレッシブであれば失敗してもGood try!としっかり誉める。客観的にみて上手いわけでもよい成績をあげたわけでもないのに自信満々な子どもたちは、はっきりと自己主張する。投げたい子は「ピッチャーをやりたい」とコーチにアピールする。そして、試合はもちろん練習にも必ずついてくるし、プロのコーチによる有料のプライベートレッスンを受けさせるほど熱心な野球パパたちの存在。父親たちと監督やコーチとのあいだで繰り広げられる選手起用をめぐる激しい衝突、チーム内の頻繁な選手の離脱や入れ替え、およそ日本では経験したことのなかった状況に直面し、それに巻き込まれるなかで、親子は葛藤しながらもアメリカの少年野球に少しずつ馴染んでいく。それは自分が活かされる「居場所」を求めて自分でチームを選び、それも何度も選び直すことが可能で、チームメイトと出会ったり別れたりを繰り返しながらしなやかに強くなっていくアメリカの少年野球の価値観を、親子が発見し、受け入れていく過程でもあった。
著者の文章は歯切れが良く、読者を作品の世界にスムーズに引き込んでゆく。息子が当初アメリカでの暮らしや学校になかなか馴染めないことに暗澹とし、試合での活躍や失敗に一喜一憂し、トライアウトに落ちたりスランプに陥ったりして暗い表情の息子に胸を痛める母親の心情も率直に綴られている。しかし、著者の文章は、平易で率直な語りのなかにも客観的な分析視点が据えられていて、母親としての主観と記者としての客観的な叙述が程よく調和しており、それが本書を単なる一家族のアメリカ体験記を超えたすぐれた日米比較スポーツ文化論にもしている。読者は、この親子の体験を通じてアメリカの少年野球の実情を知る一方、改めて日本の少年野球を含めた子どもたちのスポーツへの関わり方、ひいては子育てや親子関係についても考えさせられる。
日米の異文化交流、異文化体験が語られた書物は数多い。だが、少年野球を切り口にした本書は、まず著者の驚きを読者が容易に共感できる。そして、理解が深まり、野球の技術があがり、気がつくとサイレントピリオドの長かった息子は「お前、日本語なんてわかるの!?」とチームメイトに言われるほどになり、と母子の成長もわかりやすい。そしてその間に、読者に日本の少年スポーツや文化の違いを考えさせ、最後はスポーツの価値を改めて示している。著者は家族からいいテーマをもらった。
前半は彼我の違いの目立つ叙述が多いが、アメリカの野球に親子一体になって打ち込むうちに、文化の違いを越える人間としての共通の地金がだんだんと見えてくるのがこの作品の面白い所でもある。子どもに期待を寄せ、その一挙手一投足に一喜一憂する親の情は変わりがない。自分の子ばかりでなくチームメイトにも気配りをしてやさしい言葉を掛ける親もいるし、親同士お互いに批判し合って傷つき、メールで慰められれば涙を流すような繊細さはもちろんアメリカ人にもある。親の批判を受けて辞めたトニーコーチとの再会の話などは、なかなかしんみりさせられる。
近年、ますます指摘されることの多い日本人、特に若者のコミュニケーション能力不足の問題が頭をよぎり、太郎がたのもしく感じられる。文武両道とか、心身を鍛えるといった日本の伝統的な価値観、あるいは、体育・スポーツの意義といった表層的な指摘ではなく、エリートでもなんでもない一人の少年が育っていったプロセスでスポーツが有形無形の力を与えたという現実は嬉しい限りである。
■優秀賞
国立競技場の100年: 明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ

後藤 健生(ごとう たけお)(発行:ミネルヴァ書房)
選評:
90年前に竣工した国立競技場(当時は明治神宮外苑競技場)は日本のスポーツのメイン会場として多彩なスポーツイベントが行われてきた。本書は競技場という「場」に焦点を当てるというユニークな手法で、そこで展開されたスポーツの内容とそれを生み出した社会と人間のありように目配りした近代日本スポーツ史である。
全9章で構成されるが、その要点は以下の通りである。
・第1章 明治神宮の造営と競技場
明治大帝のモニュメントとしての明治神宮造営がどう行なわれたかを検討する。日本最大の「スポーツ・コンプレックス」を作るという構想に、明治から大正に入り、近代化の成果に自信を持って先進国の仲間入りをしようとする当時の人々の意気込みが感じられる。神宮の造営には青年団がボランティア参加して大きな役割を果たしたことが分かる。
・第2章 最新の設計思想に基づいた明治神宮外苑
まずはスタディアム建設の歴史がギリシャ、ローマの昔から語られ、1920年代の世界的潮となった大規模スタディアムの建設に日本もまた参加しようと、最新の設計思想を導して検討が行われたことが語られ、競技場の基本的なレイアウトが示される。東の神宮に対する西の甲子園の建設事情も紹介している。
・第3章 明治神宮大会の開催と1920年代の日本のスポーツ
ハードからソフトへ目を移し、完成した競技場でどんな種目が競われたか、トラック競技、2種のフットボール(いわゆるサッカーとラグビー)、その周辺の施設での武道、野球など当時のスポーツの全容が紹介され、プロとアマの問題、それまでの学生中心を脱して競技団体が育ってくること、文部省と内務省の確執(昔からやっていたのだ)等が話題となる。
・第4章 外苑競技場での国際大会、そして幻の東京オリンピック
競技場は国際的なスポーツ交流の場となる。なかでも日比中を核とした「極東選手権大会」が注目された。特に第9回大会(1930年)は50万人の観客動員を成功させ、ここからオリンピックのロス大会、ベルリン大会を経て、1940年の東京オリンピック開催が決定する。
・第5章 戦中・戦後の明治神宮外苑と日本のスポーツ
戦争の激化によりオリンピックは返上に至り、軍国主義化が急速に進む。スポーツはしだいに思想善導の道具となり、開戦後は軍事訓練の手段とされる。神宮競技場の出陣学徒壮行会に象徴されるように、スポーツそのものが否定され、敗戦を迎える。この章はそのまま占領軍に接収された競技場の使われ方に続く。スポーツが自立を失ったことは戦前戦後のこの時期の特徴だった。また、皇室とスポーツの関わりにも触れている。
・第6章 復興の槌音―国立競技場の建設
敗戦後の復興と共にスポーツも息を吹き返す。それを主導したのは1958年のアジア大会の開催であった。大会に向けて競技場は解体され、新競技場の建設が始まる。その設計の考え方や完成までの歩みが辿られる。アジア大会は盛会のうちに終わるが、スポーツと政治の関係、南北朝鮮や中国―台湾の対立にスポーツは否応なく巻き込まれていく。
・第7章 東京オリンピックの開催
アジア大会の成功をバネに、日本はオリンピック招致に向けて運動を続け、ついに1964年東京オリンピックの開催を勝ち取る。決定までの紆余曲折の歩み、競技場の改造、そして国を挙げてのオリンピックへの熱狂、東京大会の進行の様子、さまざまなエピソードが語られる。また、オリンピックを機に交通体系を始め、都市インフラの整備が飛躍的に進んだことが示される。
・第8章「企業アマ」からクラブスポーツへ
オリンピックのその後、大会としては3年後ユニバーシアードがあったが、75000人収容のスタディアムをどう使っていくかが大きな課題となった。陸上競技では埋まらず、企業が支えるサッカーや、70年代後半からのラグビーが集客に貢献する。ブームが引いた後は93年に成立したJリーグが改めて競技場に客を呼び寄せた。しかし、2002年のワールドカップを最後の華として、それからは全国各地に大規模スタディアムの建設が進んで、国立競技場は岐路に立たされる。
・終章 2020年オリンピック開催と国立競技場の将来
東京オリンピックの再来が決まり、競技場の建て替えが始まろうとしている。しかし、新スタディアム構想はデザインだけが先行し、これからの使い方は見えていない。
スポーツの容れ物である競技場とその内容であるスポーツの動きを相互に関わらせながら語りを進め、さらにスポーツの背景となる社会の変化、もろもろの事件とそれをめぐる人間模様、さらに国際政治の変化、国家間の対立、戦争、その背後にある経済問題にも目配りして立体的なスポーツ史を書き切っている。競技場での主要なイベントに注目して時代区分を設け(明治神宮大会、極東選手権大会、アジア大会、オリンピック、ワールドカップ等)、大会の内容を通してその時代のスポーツの全体像を浮かび上がらせている。研究書として見たとき、構想が明確で、資料(参考文献、年表、事項・人名索引)も手堅く、充実している。もっとも、事実を淡々と積み重ねていく書き方で、なぜそうなったのかという解説や分析にはもう一つ突っ込みがほしい所もある。他方、スポーツ・ノンフィクションとして見ると、外苑競技場という舞台で、日本のスポーツ史を彩る競技やイベントがテンポ良く展開されて興味が尽きない。あたかも魔法の絨毯に乗せられて、青山練兵場あとの空き地に競技場が作られ、大勢の人々で賑わった大正時代から、空襲の日々を経て、青空の東京五輪開会式、華やかなJリーグ開幕、そして取り壊しを前にして最後のスポットライトを浴びている現在までのパノラマを見たような気がしてくる。