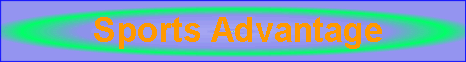|
|
|
ワールドシリーズでバーチャルテレビ広告
(杉山 茂/スポーツプロデューサー) | | 松井秀喜の登場なるか、で、ワールドシリーズ(10月18日開幕)への関心が、かつてなく高い。
1903年(明治36年)、ナショナルリーグのピッツバークとアメリカンリーグのボストンによる第1回から、ちょうど100年。アメリカ国内向けテレビ中継が行われて55年。節目の年といおうか、新しい時代の幕開けといおうか。その舞台に日本人選手が参加できるなら、これまた、記憶にとどめられることになる。
そのテレビ中継で、画期的な手法が採用される。
担当するFOXが、ワールドシリーズでは初めて、コマーシャルに「バーチャル・ロゴ」を採用するというのだ。
フィールドのフェンスやスコアボードなどに掲示されている広告スペースへかぶせるようにテレビ画面上では、コンピューター処理したスポンサーのロゴを露出するものである。
つまり、スタディアムと家庭では、同じ現場の風景でも広告の“内容”が違うことになる。
ワールドシリーズ以外でのスポーツ中継では、すでに試みられており、日本でもテストが行われている。
ビデオテープでプレーが再生された時、広告が違ってしまうなど課題もあったが、今回、どう解決するのか、興味深い。
テレビ中継での「バーチャル演出」は、最近ではアメリカンフットボールのダウン更新ラインの表示が好例だ。
実際のフィールドでは見られぬラインをめぐってのスリルをテレビ画面では味わえる。
競泳の国際レースで、各レーンに国旗のデザインが浮かび上がるのも、現場にはないサービスである。
「バーチャル」は、古くミュンヘンオリンピック(1972年)のボート競技で水面には引けぬフィニッシュラインを、テレビ画面では電気的に工夫して見せている。
今回は、ワールドシリーズというスーパーイベントのテレビ広告に採用されるという点でインパクトは強い。
テレビに映ることをメリットに、高額を呼ぶスタディアム広告料に、影響も出そうだ。
テレビ側にしてみれば、スタディアムやアリーナでの広告が映っても多くの場合、収入にならないのだから、「バーチャル」への研究は、いっそう進むだろう。
ところで、ワールドシリーズのアメリカ国内向けテレビコマーシャル料は、30秒で、平均32万5000ドルの史上最高をマークする見通しだ(この金額は第5戦まで。第6,7戦はやや値が下がる)。
ワールドシリーズの人気は下がり気味といわれていただけに、注目される。
もっとも、史上最高といっても、スーパーボウルの30秒平均200万ドルには遠く及ばない。
32万ドルは、スーパーボウルでは1982年の値段である。 | PageTop |
| アメリカに「二世選手」が多い訳
(賀茂美則/スポーツライター/ルイジアナ発) | | 9月28日、ナショナルフットボールリーグ(NFL)の試合で、大記録が生まれた。
インディアナポリス・コルツのクオーターバック、ペイトン・マニングが一試合でタッチダウンパスを6回成功させたのだ。
これまで一試合で7回成功させた例があるが、6回というのも相当珍しく、1991年以来だと言う。
この偉業をプレスボックスで見ていたのが、ペイトンの父親、アーチー・マニングである。この試合の相手、ニューオーリンズ・セインツ始まって以来の名クオーターバックである。
このマニング家の栄光は、この二人に留まらない。ペイトンの弟、イーライ・マニングは、父親アーチーの母校、ミシシッピ大学でやはりクオーターバックを務め、来年はNFLに入ることが確実視されている。
アメリカではこのように、親子や兄弟そろってプロスポーツ選手になるケースが非常に多い。有名なところでは、大リーグ、シンシナチ・レッズの強打者、ケン・グリフィー・ジュニアがいる。デビュー直後の1990、91年には、父親のケン・グリフィー・シニアと一緒にシアトル・マリナーズでプレーしたこともある。
6月に行われた今年の大リーグのドラフト第1位は高卒新人、デルモン・ヤングだが、彼の父親、ラリーはコーチであり、兄のドゥミトリ・ヤングはオールスターゲームにも選ばれたデトロイト・タイガースの強打者である。他にも今年の大リーグドラフトで選ばれ、大リーガーを父親に持つ選手は十指に余るほどである。
以前このコラムで紹介したルイジアナ州立大学出身のクオーターバック、ジョシュ・ブーティにしても、その父親はルイジアナで毎年1、2位を争う名門校のコーチで、弟は二人とも大学フットボールの選手である。
翻って日本では、親子や兄弟でプロ選手になるというケースは非常に稀である。長島一茂やカツノリの例があるにしても、子どもの方は一流とは言いがたい。
それでは、なぜアメリカでは親子や兄弟そろってプロ選手になるケースが多く、日本では少ないのだろうか。
ズバリ言って、アメリカでは父親が子どものスポーツに関わることが多く、日本では少ないからではなかろうか。
アメリカの親、特に父親を見ていると、子どものスポーツに力を入れている場合が非常に多い。休みともなればバッティングセンターにつき合い、試合は欠かさず見に来て、子どもにアドバイスをする。子どものスポーツが趣味、とすら見える父親が数多い。
人間の運動能力というものは、どうやら生まれつきの部分と発育の過程で形成される部分の両方がある、ということがわかってきた。一言で言えば、生まれつき持った能力の限界までたどり着けるかどうかは、子育てによるのである。
筆者の次男が去年入っていたチームに野球のうまい子どもが8人いたが、このうち6人の親は元プロ野球選手1人を含め少年野球の監督やコーチをした経験があった。
つまり、小さい頃に親と遊んだ方が、子どもは運動ができるようになるのだ。スポーツのできる父親、特にプロ選手ともなれば、子どもに助言するのがアメリカでは当たり前だ。兄弟がいれば、どちらも父親の薫陶を受けるので、兄弟選手も多くなる道理である。
大リーグのオールスターゲームで行われてたホームラン競争で、外野に飛んだボールを追っていたのはみな選手の子供たちだ。ここから明日の大リーガーが出てくるのだ。
日本はどうだろうか。長時間労働と通勤、さらには休日出勤もあったりで、父親が子どものスポーツの相手をするということは稀である。さらに、日本のティーンエイジャーは、親との付き合いをことさら避ける傾向にあり、親が試合を見に来たり、技術的なアドバイスをするのを歓迎しない。
僕の知り合いに日本で有名だったプロ選手で、プロ野球チームのコーチをしている人がいるが、その息子が大学を経て社会人野球をやっていても、技術的なアドバイスをしたことは全くないという。アメリカでは考えられないことだ。
日本では父親が子どもにスポーツを教えることは少ない、という事実に、一つだけ大きな例外がある。イチローに野球を教えた「チチロー」である。イチローが3年生の時から高校の寮に入るまで、7年間毎日バッティングセンターにつき合い、ノックをし、イチローの投げるボールを受けたのである。
「チチロー」が会社員ではなく、自分の経営している工場から毎日3時半に抜けだせたという事実は、父親と子どもの関係を語る上で、象徴的な気がするのだが、いかがだろうか。 |
PageTop |
| 日本女子オープン、服部がプレーオフを制して2度目の優勝
(早瀬 利之/作家) | | 久しぶりにいい試合を見た。
今年の日本女子オープンは千葉CC野田コースで開催され、プレーオフのすえ、服部道子(35歳)が9年ぶり、2回目の優勝をとげた。
プレーオフ2ホール目16番グリーン上の明暗は、2オンした李知姫(27歳)が90%優勝を決めたかに思えた。上から5メートルのバーディーパットを90センチ右上につけ、軽いフックラインを残したが、まさか、カップのフチにけられて右を通過するとは、思いもしなかった。
李知姫のパーパットは、カップの右サイドの内側を狙えば入っていた、というのは結果論であるが、1打の攻防がかかった時は、異常な心理になる。曲がると思ってカップの右上を手堅く狙ったが、ちょっと強めのタッチが、右カップのフチを抜けた。
「フックラインはストレート気味に」と言ったのは青木功だが、早い下りのフックラインをふくらませて狙ったばかりに外れた。
問題は、かえしのボギーパットである。下からのストレートパットが、またも右に抜けて、ダブルボギーを叩き、絶望視された服部に、運がめぐってきた。
服部は、ティショットを右ラフ。そこから7番ウッドでグリーンを狙ったが、フックさせて、絶対に行ってはならない左のカラーに打ち込んだ。そこからのアプローチは2メートルもオーバーさせ、パーパットも外した。そのあとの李知姫の短いパーパットだけに、勝負あったかと思えた。
結果は李知姫が4パットのダブルボギーを叩いて自滅した。プレーオフとは実に残酷なものである。見る方にとっては同情と悲運が今も残っている。 |
PageTop |
| スポーツに何もつけ加えるな
(佐藤次郎/スポーツライター) | | これはもう何度でも言わねばならない。スポーツというものに対するテレビの考えとは、いったいどうなっているのか。このままの状況をさらに続け、エスカレートさせていこうというのか。もしそうなら、視聴者として、またスポーツ愛好者として言い続けなければならない。
「その考え方は間違っている。結果的にスポーツをおとしめることにもつながっている。スポーツの魅力はスポーツそのものにあるのであって、何もつけ加える必要はないのだから」
このことである。
たとえばここ何年かは、主要競技の世界選手権のように大きなスポーツ大会の中継となると、総合キャスターとして、またゲストとしてスタジオにタレントや芸能人が登場し、応援団よろしく長々とおしゃべりをするのが当たり前になっている。レポーターとして現場にも現れる。また、競技の中継は中継で、大げさで内容の乏しい絶叫調のアナウンスが続く。
選手におかしなキャッチフレーズをつけるのも大はやりである。選手に対して礼を失する命名も少なくない。大会をショーアップしようとして妙な演出をする場合もある。そういえば、いつかは柔道大会で、まるでプロレスのような形で選手を登場させたこともあった。あれは柔道連盟が企画したわけではあるまい。先だっては、ボクシングの中継に大勢のゲストやら他の企画やらが登場して驚かされたところだ。
例を挙げていけばきりがない。テレビはスポーツ中継を限りなくバラエティ番組に近づけているのだ。つまり、スポーツそのものを伝えようとしているのではなくて、スポーツをひとつの材料としたバラエティをつくっているのである。
担当者たちは必ず言う。「スポーツを知らない人にも興味を持ってもらうためだ」と。しかし、実際にそうなっているだろうか。確かに人気タレントや演出にひかれて見てみようと思う人もいるだろう。だが、こうした番組のつくり方でスポーツ本来の面白さが伝わるとは思えない。それに、元々のスポーツファンたちは、バラエティづくりの中継に嫌気がさして早々にテレビを消してしまうのではないか。
この流れは当分止まらないだろう。しかし、すべてのテレビ関係者がこれをよしとしているわけではあるまい。本当にスポーツのことを理解している者が、ごく当たり前な形でスポーツ番組をつくってみれば、そっちの方がずっと面白くて、視聴者にも受けることがわかるはずだ。
スポーツには演出も飾りも賑やかしもいらない。スポーツそのものが大いなる魅力を持っているのだから。テレビが早くそれを思い出すことを祈りたい。 |
PageTop |